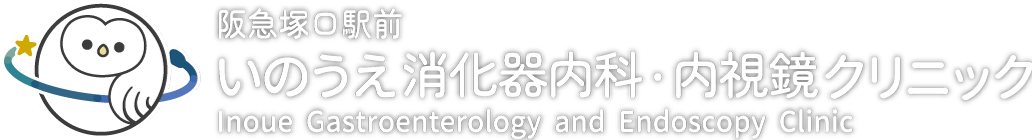目次
尼崎市の阪急塚口駅前いのうえ消化器内科・内視鏡クリニックです。
コーヒーに含まれるカフェインが腸の動きに影響を与えることは広く知られていますが、その摂取量によって効果が異なる可能性があるという、興味深い研究結果が2025年6月に報告されました。
👉 研究論文はこちら
この研究では、アメリカの大規模な健康調査(NHANES)のデータを用いて、カフェインと排便習慣の関係が分析されました。対象は12,000人以上の成人で、腸の状態(正常、便秘、下痢)とカフェイン摂取量との関連が評価されています。
カフェインと便秘・下痢、それぞれの関係性
・下痢との関係
カフェインの摂取量が多い人ほど、慢性的な下痢になるリスクが高まる傾向がありました。具体的には、カフェインを1日100mg多く摂取するごとに、下痢のリスクが4%ずつ上昇するという結果です。
・便秘との関係
一方で、便秘との関係は一筋縄ではいかず、カフェイン摂取量との間に「U字型の関係」があることが明らかになりました。1日あたり約200mg(コーヒー約2杯程度)までは便秘リスクが下がるのですが、それを超えると逆に便秘の可能性が高くなるという、逆効果も示唆されています。
・高齢者にとってのメリットも
特に注目すべきは、60歳以上の高齢者では、カフェインの摂取量が増えることで便秘のリスクが14%も減るという結果です。年齢層によって影響の出方が異なることも示されました。
摂りすぎ注意。自分に合った「適量」を見極めましょう
この研究から得られる重要なメッセージは、「カフェインは量次第で薬にもなり、害にもなりうる」ということです。体質や年齢、生活習慣によって適切な摂取量は変わるため、安易に「たくさん飲めば便秘が治る」とは言い切れません。
また、便通改善を目的にコーヒーを飲むなら、1日2杯程度にとどめ、飲みすぎに注意しましょう。とくにカフェイン入りのエナジードリンクやサプリなどを併用している方は、総摂取量に気をつける必要があります。
健康的な便通のために、生活全体を見直してみましょう
当院では、カフェインに頼りすぎない自然な便通改善法もご提案しています。
- ・朝の軽いウォーキング
- ・水溶性食物繊維を含む野菜・海藻・果物の摂取
- ・発酵食品(ヨーグルト・味噌・納豆など)の活用
- ・睡眠やストレス管理も大切です
それでも改善が見られない場合は、便秘の背後に病気が隠れている可能性もあります。必要に応じて大腸カメラなどの検査をご案内いたしますので、ぜひご相談ください。